普段の会話や文章で、何気なく使っている慣用句。短い言葉で情景や意味を伝えられる、とても便利な表現ですよね。
でも実は、多くの人が「本来の意味とは違う意味」で使ってしまっている慣用句がたくさんあるんです!
あなたは大丈夫?意外と間違えている人が多い「あの慣用句」
あなたは、次の慣用句の意味、自信を持って答えられますか? さっそくですが、ドキドキの慣用句クイズに挑戦してみましょう!
【ドキドキ!慣用句三択クイズ】
「破天荒」の正しい意味は、次のどれ?
- A:型破りで豪快な人や様子。(良い意味で)
- B:前代未聞の偉業を成し遂げること。
- C:でたらめで無茶苦茶な様子。(悪い意味で)
さあ、どれを選びましたか? 正解は記事の最後に発表しますので、ぜひ最後まで読んで確かめてみてくださいね!
この記事では、この「破天荒」をはじめ、多くの人が間違って使ってしまいがちな慣用句の【本当の意味】と【面白い由来】をご紹介します。
言葉の奥深さに触れることで、あなたの語彙力がアップし、普段のコミュニケーションがもっと豊かになるはず。知らずに恥をかくことも防げますし、きっと誰かに話したくなる面白い雑学がたくさんですよ。
さあ、一緒に言葉の旅に出かけましょう!

なぜ、慣用句は「間違って」伝わってしまうの?誤用の背景を探る
そもそも、なぜ慣用句は本来の意味とは違う形で広まってしまうのでしょうか?そこにはいくつかの理由が考えられます。
- 言葉は生き物だから: 言葉は時代とともに変化し、使われ方が変わっていくことがあります。慣用句も例外ではありません。
- 見た目や響きからの連想: 漢字の並びや音の響きから、本来とは違うイメージや意味を連想してしまい、それが広まってしまうケースです。
- 誤った情報が伝播: テレビ、インターネット、人づての会話などで、誤った使い方がそのまま伝えられてしまうこともあります。
しかし、その「間違い」の背景や、本来の意味を知ることで、言葉が持つストーリーや奥深さに気づくことができます。そして、正しく使うことで、より伝えたいニュアンスを的確に表現できるようになりますよ。
知らないと恥ずかしい?間違われやすい慣用句5選【正しい意味と由来】
それでは、多くの人が間違って使っていると言われる代表的な慣用句を5つご紹介します。あなたはいくつ正しく理解しているでしょうか?
「破天荒(はてんこう)」
▲よくある間違い(誤用): 「型破りで大胆」「常識にとらわれない豪快な人」といった、良い意味で使われる。
★本当の意味: 「前代未聞の偉業を成し遂げること」「誰もできなかったことを初めて行うこと」
💡由来・語源エピソード: 中国唐代の故事に由来します。湖南省のある地域からは、それまで一度も科挙(高級官僚になるための試験)の合格者が出たことがありませんでした。この状況を「天荒」(開墾されていない未開の地)と呼びました。そこに初めて合格者が出た時に、「天荒を破る」(未開の状況を打ち破る)と言われたことが語源です。つまり、それまで誰も成し遂げられなかったことを初めてやり遂げる、という意味なんです。
✅正しい使い方(例文):
- 「彼は〇〇業界で初の快挙を成し遂げ、まさに破天荒な人物として歴史に名を刻んだ。」
- 「彼女の研究は、既存の学説を覆す破天荒な発見となった。」
「的を得る(まとをえる)」
▲よくある間違い(誤用): 「要点をうまく捉える」「核心をついた発言をする」という意味。
★本当の意味: 「的を射る(まとをいる)」が正しい表現で、「物事の核心や要点を正確にとらえる」という意味です。 「的を得る」は誤用とされることが多いです。
💡由来・語源エピソード: この言葉は弓道から来ています。「的を射る」とは文字通り、弓で「的」を「射る(打ち当てる)」ことです。これが転じて、物事の要点を正確に捉える、という意味になりました。「得る」は手に入れるという意味なので、「的を得る」だと、的を物理的に手に入れるような不自然なニュアンスになります。現代では「的を得る」も耳にすることが多く、許容される場面もありますが、本来は「的を射る」が正しいとされています。
✅正しい使い方(例文):
- 「彼の発言は議論の的を射ていた。」
- 「問題の核心を的確に射る分析だった。」
「慇懃無礼(いんぎんぶれい)」
▲よくある間違い(誤用): 「非常に丁寧すぎる態度」「過剰なほど礼儀正しい様子」という意味で使われることがある。
★本当の意味: 「表面上は非常に丁寧だが、内には傲慢さや無礼な気持ちがあり、それが態度や言動の端々に現れていること。」
💡由来・語源エピソード: 「慇懃(いんぎん)」は非常に丁寧で礼儀正しい様子、「無礼(ぶれい)」は礼儀を欠いている様子です。この二つの正反対の意味を持つ言葉が組み合わさることで、「見せかけの丁寧さの裏にある無礼さ」という意味が生まれています。これは、ただ単に丁寧なだけでなく、その丁寧さがかえって嫌味に聞こえたり、相手を見下しているように感じられたりする態度を指します。言葉だけは丁寧なのに、目が笑っていない、上から目線が透けて見える、といったイメージですね。
✅正しい使い方(例文):
- 「彼の態度は表面上は丁寧だったが、どこか慇懃無礼な響きがあり、不快に感じた。」
- 「新入社員のその慇慇無礼な言葉遣いが、上司の反感を買った。」
「檄を飛ばす(げきをとばす)」
▲よくある間違い(誤用): 「激励する」「応援する」「エールを送る」といった、励ましの意味で使われることが多い。
★本当の意味: 「自分の主張や考えを広く人々に知らせて同意を求めたり、決起を促したりすること。」「強く訴えかけて行動を促すこと。」
💡由来・語源エピソード: 「檄(げき)」とは、古代中国で使われた、人々に自分の意見や行動の理由を伝え、賛同や協力を求めるための文書や木札のことです。漢の陳勝・呉広の乱で使われた「檄」が有名です。これを「飛ばす」というのは、遠方へ送る、広く伝えるという意味です。つまり、「檄を飛ばす」とは、リーダーなどが自分の思想や方針を明らかにし、人々を鼓舞して行動を起こさせる、という強いメッセージ伝達の意味合いが本来なんです。「頑張れ!」と励ます、というよりは、「我々はこうするぞ!皆も続け!」と訴えかけるイメージに近いですね。
✅正しい使い方(例文):
- 「党首は全国に向けて、改革への決意を示す檄を飛ばした。」
- 「経営者は社員に対し、現状打破を訴える檄を飛ばした。」
「話のさわり(はなしのさわり)」
▲よくある間違い(誤用): 「話の冒頭部分」「導入部分」という意味で使われることが多い。
★本当の意味: 「話や文章の中で、最も聞かせたい、最も重要な(聞きどころ・見どころの)部分。」
💡由来・語源エピソード: この言葉は、日本の伝統芸能である浄瑠璃や長唄の世界に由来します。「さわり(触り)」とは、これらの音楽の中で、聞く人の心をグッと掴む最も印象的で聞き応えのある部分を指しました。これが転じて、話全体の中で一番面白かったり、感動的だったり、重要だったりする「核心部分」を意味するようになりました。よく誤用で「話のさわりだけ聞かせてよ」と言いますが、本来の意味で使うと「話の一番面白いところだけ聞かせてよ」という意味になってしまいます。
✅正しい使い方(例文)::
- 「彼の講演は長かったが、最後の部分がまさに話のさわりだった。」
- 「この小説のさわりは、主人公が真実に気づくあの場面だ。」
正しい慣用句を知っているとどんないいことがあるの?
さて、ここまで間違えやすい慣用句をいくつか見てきましたが、「正しい意味を知って、何か良いことあるの?」と思うかもしれませんね。
正しい慣用句の知識は、あなたのコミュニケーションをさらに豊かにしてくれます。
- 意図した通りに相手に伝わりやすくなり、コミュニケーションの誤解を防げます。
- より正確で、洗練された言葉遣いになり、知的な印象を与えられることも。
- 言葉が持つ背景や文化を知ることで、日本語の奥深さをもっと感じられるようになります。
- 今回のような雑学は、話の引き出しを増やし、会話を盛り上げるきっかけにもなりますよ!
難しく考えすぎず、「へぇ〜、そうなんだ!」くらいの軽い気持ちで、言葉の豆知識を楽しんでみてください。
まとめ:言葉の旅は面白い!今日から使える慣用句知識

今回は、間違って使われがちな慣用句の中から5つをピックアップして、その正しい意味や面白い由来をご紹介しました。
【お待たせ!クイズの答え合わせ】
さて、記事の冒頭で出題した「破天荒」のクイズの答えを発表します!
「破天荒」の正しい意味は…?
正解は… B:前代未聞の偉業を成し遂げること。
この記事を最後まで読んだあなたなら簡単でしたでしょうか?「型破り」という意味で使っていた方も多いのではないでしょうか。 元々は誰も成し遂げられなかったことを初めて行う、という強い意味合いなんですね。
言葉は時代とともに変化しますが、そのルーツを知ることは、言葉の面白さを再発見することに繋がります。
今回ご紹介した以外にも、間違えやすい慣用句や、面白い由来を持つ言葉はたくさんあります。ぜひ、これをきっかけに、他の言葉にも興味を持ってみてください。
言葉の世界は知れば知るほど奥深く、あなたの日常を少しだけ豊かにしてくれるはずです。
当ブログでは、他にも雑学系記事を投稿しています。ご興味があれば、そちらもご覧ください!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
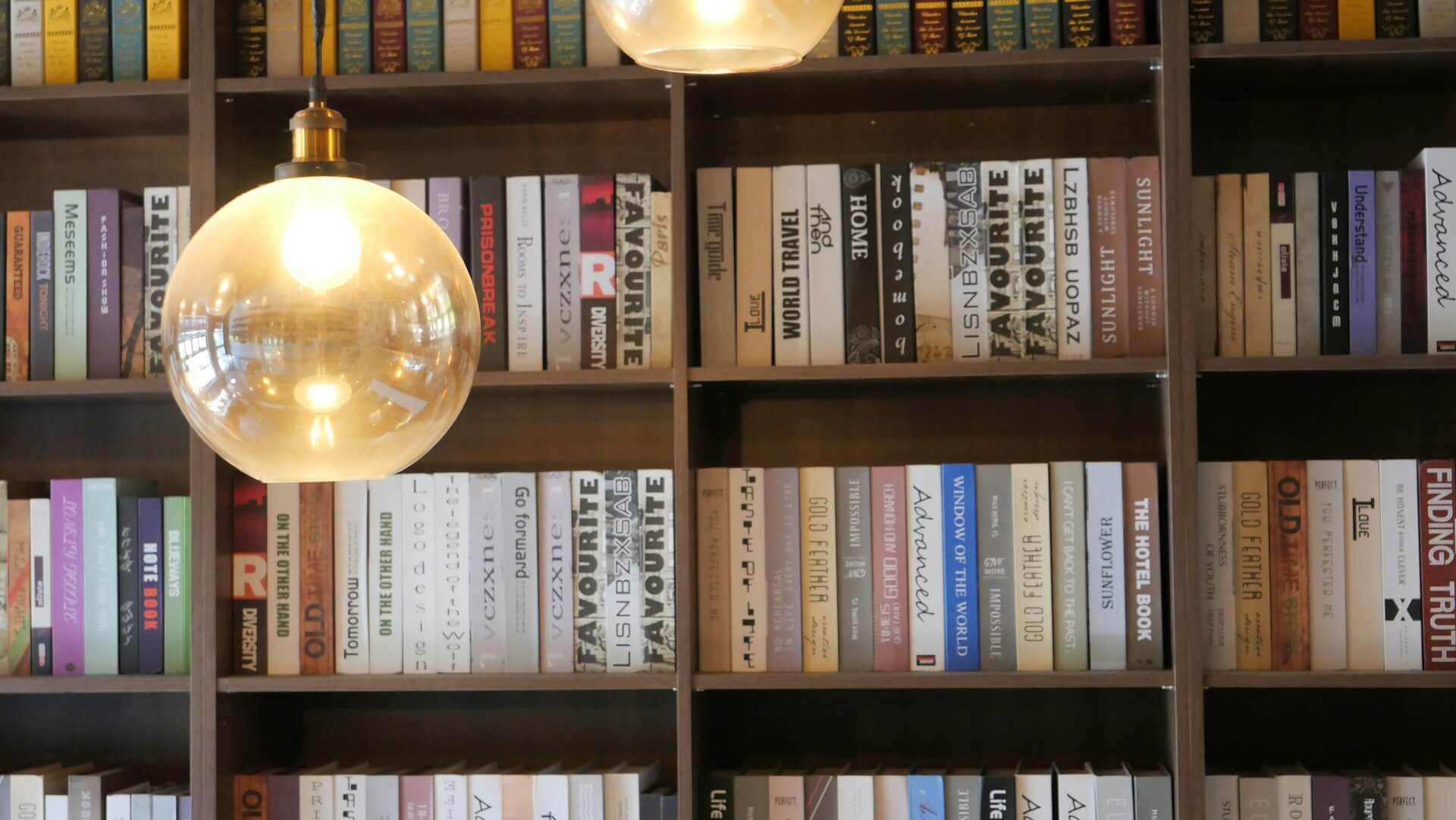



コメント